こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
社会人大学院生日記の1月号です^^
2025年一発目の大学院生日記です。
さて1月のネタは「大学院生の仕事、学部生との関わり」です。
ではやっていきましょう!!
今回のブログは下記のネタに関連しています^^
併せてどうぞ^^
学部生との関わり
このワークショップでは
様々な年齢の医学生、薬学生、看護学生と関わることができました。
学生のうちから、実際に働いている職種と関わり
ワークショップを行うなんて、意識の高いことするなんて
自分が学生だったときには考えたこともありませんでした^^

ラウンドワンでWCCFばっかりやっていたもんな

懐かしくて死ぬ。ネドベドあたった時最高だったなぁ

そんなことしているから再試験だらけだったんだぞ。

父ちゃん、母ちゃんごめん
戯言は置いておいて
本当にすごいですよね。
今回のワークショップの企画は医学生が持ってきてくれたものです。
「学生のうちから連携を学びたいです^^」

^^;;
そんなこんなで、新年一発目にこのワークショップを行い
割と好評に終わったのでした。
このときに関わってくれた
医学生さん、薬学生、看護学生さんとは今後もつながっていたいですね
地域医療、チーム医療を行っていく仲間になっていきたいです。
で??
って思いましたか^^;
このブログ記事で言いたかった主題は
「大学院生は学部生の教育も仕事の一つ」ということです。
多分基礎研究をしている先生方は
学部生の研究を見ることもあるでしょう。
指導教官の指示を受けた大学院生が、学部生を指導する感じですよね。
ただ、私は社会人大学院生なので
研究室にいることはありません。
そんな中で、どのように教育するかというと
院外、学外での活動になるかなと思っています。
今回の機会は、準備がかなり大変でしたが
かなり良い経験をすることができました。
大学院生を目指す方は、このように学部生の指導、教育があるかもしれないと
思っていたほうだ良いですね。
教育と言うキーワード
今回は「教育」というキーワードに触れていきます。
皆さんは成人ですよね??
学部生も大体は成人なので、その成人にどの様な教育方法が出来るかと言うことで
「成人学習理論(アンドラゴジー)」について少し触れます。
このアンドラゴジーには「成人は子どもとは異なる学び方をする」という中心的テーマに加えて
基本原則があるようです。
アンドラゴジーの基本原則
1.学習者の自己概念
成人は自律的であり、自分の学習を主体的に管理したいと考える。
2.学習の必要性の認識
成人は自分にとって必要な学習でないと意欲を持ちにくい。
▶仕事で使用しない知識であれば、全く手を出そうとしませんよね?必要にかられて学習するということでしょうか。
3.過去の経験の活用
成人は豊富な経験を持っており、学習の際にそれを活かしたいと考える。
▶誰しも思うことですよね。
4.学習の準備性
成人は、人生の特定の状況(職業上の課題や個人的な目標)に直面したときに学習意欲が高まる。
▶2番と同じ様な考え方でしょうかね。
5.学習の方向性
成人は実践的な学習を好み、理論だけでなく、実際に役立つスキルを求める。
▶学んだことを実技でも活かしたい。
6.内発的動機付け
成人は外的な報酬(成績や資格)よりも、自己実現や成長といった内的な動機によって学ぶ傾向がある。
この様な原則から
成人は自分で学習しようという意欲があるという反面
それを阻害する因子も存在している。
こういった阻害因子に打ち勝つためには
「指導者が必要」ということで

大学院に行きませんか?
ということでした^^
でも皆さんわかっていますよ。
行動変容のステージ(引用HP:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-07-001.html)が変わってきていることを!
私のブログを見てくれている人は
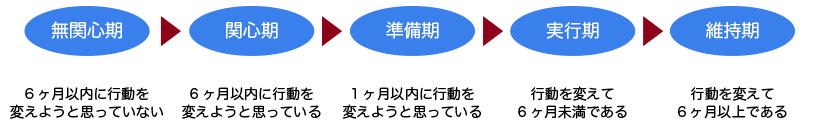
無関心期から関心期に移行してませんか??
またはそれ以上では???

そうだったとしても、このブログではないことは確か。
まぁいいとして
成人学習理論を学ぶには、別の書籍を提案しますが
今回のワークショップでは、成人学習者に対して
能動的な学習環境を提供したと思っていますが
成人学習者の特徴を理解する(自己主導性、動機づけ、経験の影響)について
少し弱かったのかなと思っています。
詳しくは、下記ブログを見てくださいね^^
「場のデザイン」というところに「失敗談」を書いています。
まとめ
今回のブログ記事では
薬剤師の仕事とはかけ離れた、大学院生の仕事というテーマで
教育を書きました。
ただ、皆さんの仕事の場においても
教育を切って離すことはできないのではないでしょうか
その際に活用できるかもしれない「成人学習理論」
動機づけにどの様なアプローチが出来るか
部下に「黙ってやれ」「いいからやれ」ではついてきません。
私と一緒に勉強していきましょう。

このネタ大学院生日記か?

まぁいいんだよ。また来月お会いしましょう。
来月は2回目の中間発表会があります^^^^^^

ちゃんちゃん。
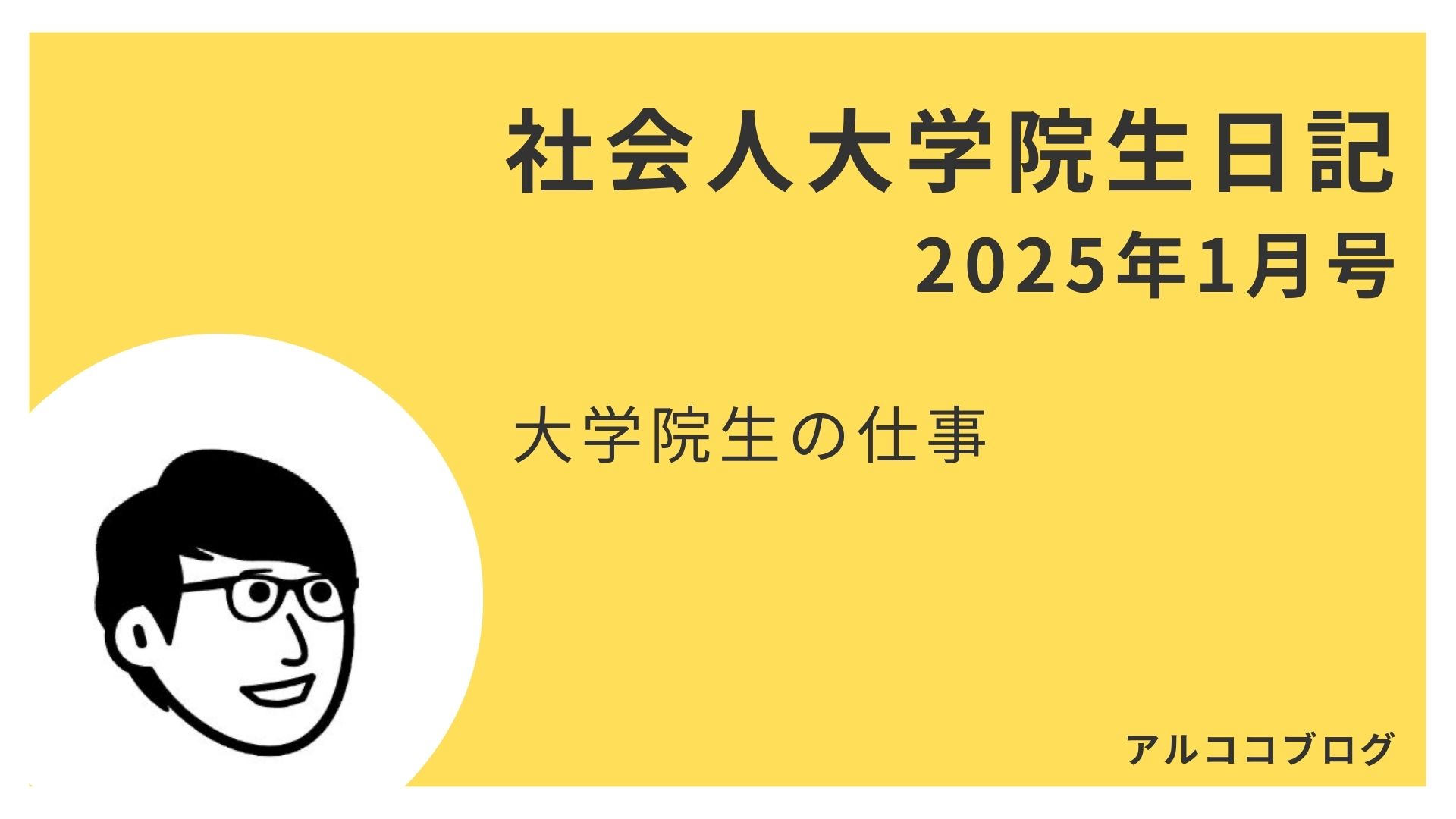

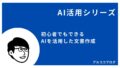

コメント