こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
病院薬剤師のいる日常シリーズの4回目です。
2回目、3回目と「点滴」「抗がん剤」に関係する記事を書きました。
今回は薬の飲み合わせについて書こうと思います。
このシリーズは病院薬剤師の仕事を紹介するものですが
飲み合わせについては、病院薬剤師だけではなく
保険薬局の薬剤師も確認しています。

「サプリも飲んでるんだけど大丈夫なの?」

「飲み合わせが悪いといけないから、この薬は飲まないほうがいいんですよね?」

心配だと思いますが、自己判断で服薬をやめないようにしてください。
安心して薬を飲めるようにチェックします。
そんなふうに、日々の生活の中でふと気になる「飲み合わせ」について、
薬剤師はどこまでチェックしているのか?
そもそも飲み合わせが悪いと、身体にどんな影響があるのか?
実際の例も交えてご紹介します。
なにか参考になれば幸いです。ではやっていきましょう!!
この記事の音声コンテンツはこちら↓
————————————————–
このカテゴリーでは病院薬剤師を一般の方によく知ってもらうために
病院薬剤師の日常をわかりやすく(?)書いていくものです。
記事一覧はこちら↓

そもそも「飲み合わせ」って?
「飲み合わせ」とは、薬と薬、薬と食品、薬とサプリメントなどを
一緒に摂取することで、お互いの効果や副作用に影響が出ること を指します。
たとえば、ある薬が体の中で分解されるスピードが変わったり、吸収が妨げられたり、
逆に吸収が増えて効果が強まりすぎたりします。
このような変化は薬が、
「どんな経路で体に作用しているか」「どんな酵素で分解されているか」などの違いから起こります。
世の中に存在する薬やサプリメント、食品の組み合わせは膨大です。
そのため、すべての組み合わせを完全にチェックすることは現実的には難しく、
薬剤師は 「問題が出やすい」「重篤な影響が出やすい」相互作用を中心に重点的にチェック していま
す。

全部チェックしてよ!怖いわ!
飲み合わせが悪いとどんな不利益があるの?
では実際に、飲み合わせが悪いと患者さんにはどのような影響(不利益)があるのでしょうか?
具体的には次の3つのリスクがあります:
① 思わぬ副作用が出る
② 治療効果が落ちる
③ 医療費や通院の負担が増える

一つ一つ詳しく話していきますね^^
① 思わぬ副作用が出る
たとえば血圧を下げる薬が効きすぎてフラフラになったり、
眠気が強くなったり、場合によっては命にかかわる重篤な副作用が出ることもあります。
② 治療効果が落ちる
本来必要な薬の効果が打ち消され、病気がうまく治らなくなることも。
知らずに服用を続けて、治療の遅れにつながることがあります。
③ 医療費や通院の負担が増える
副作用が出たり、効果が不十分だと、余計な検査や治療が必要になる場合も。
身体にもお財布にも負担になってしまいます。
実例の紹介
薬の飲み合わせで困ったこと事が起きること
なんとなくご理解いただけましたでしょうか。

やっぱり薬飲むのやめようぜ!

何度も言いますが、自己判断での休薬はやめてください^^;
続いてその実例を紹介します。
【例1】降圧薬とグレープフルーツジュース
血圧の薬(カルシウム拮抗薬)を飲んでいる方に
「朝食のときにグレープフルーツジュースを飲むのが好き」という方がいました。
グレープフルーツに含まれる成分が薬の代謝を妨げ、
薬が体内に長く残って効きすぎることがあり、血圧が下がりすぎて
「めまい」や「ふらつき」を起こすことも。
この方には「グレープフルーツジュースは控えてもらうように依頼しました」。
グレープフルーツジュースは降圧薬だけではなく
他の薬剤にも影響することがあります。
※グレープフルーツジュース意外であればどのジュースが良いのかはここでは触れません。
【例2】ワルファリン(血液をサラサラにする薬)と納豆・青汁
心房細動の患者さんが健康のために毎日納豆と青汁をとっていました。
しかし、ワルファリン というお薬は ビタミンK と深い関係があり、
納豆や青汁(ケールなど)に豊富な「ビタミンK」が
ワルファリンの効果を打ち消してしまうことがあります。
その結果、血液が思ったほどサラサラにならず、
血栓ができるリスクが上がってしまうケースが報告されています。
なので、納豆や青汁は我慢して貰う必要があります・・・
※注意点※
最近よく使われている
・「新しい血液サラサラの薬(DOACと呼ばれるもの:リクシアナ®、エリキュース®、イグザレルト®)」
・「抗血小板薬(バイアスピリン®など)」
の場合は、納豆を特別に制限する必要はありません。
何で、どうやってチェックしているの?
では実際に、薬剤師は どんな情報を使って飲み合わせをチェック しているのでしょうか?
世の中に出回っている薬やサプリメント、食品の情報は膨大です。
そのため、さまざまな情報源を組み合わせてチェックしています。
主なものを紹介します:
添付文書
まず基本となるのが 「添付文書」 です。
これは薬を承認したときに国(厚生労働省)に提出されている公式な情報で、
相互作用が確認されている薬や注意すべき組み合わせが記載 されています。
薬剤師はこれを確認して、特に問題が指摘されている組み合わせをチェックします。
インタビューフォーム
「インタビューフォーム」 は、製薬会社が医療従事者向けに提供している
より詳しい資料です。
添付文書に書ききれなかったような
薬の吸収・代謝の詳しいデータや相互作用の研究結果 などが載っています。
薬剤師はこの情報も参考にして、より深く相互作用のリスクを判断しています。
■ 論文・学術情報
新しい相互作用や、添付文書にはまだ載っていないような情報は、
最新の医学・薬学論文 から得ることもあります。
とくに海外での報告や新薬との相互作用は、
学会発表や専門誌 にいち早く掲載されるため、薬剤師は日々こうした情報にも目を通しています。
■ UpToDate® などの相互作用チェックツール
さらに最近では、「UpToDate」 のような
臨床支援ツール も活用しています。
これは膨大な医学データベースを元に、
薬剤の相互作用を自動的に判定する「相互作用チェッカー」機能 がついていて、
実際の患者さんの服薬状況にあわせて迅速に確認できます。
こうしたツールは、最新の知見や海外の情報までカバーしており、
薬剤師にとって強力なサポートになります。
患者さんの 現在飲んでいる薬・市販薬・サプリメント・生活習慣 などを総合的に確認して、飲み合わせのリスクがないか確認します。
具体的には:
- 医療機関から出た複数の薬同士
- 医療機関の薬と市販薬・サプリメント
- 薬と食べ物や飲み物
また、医師とも相談しながら薬の変更や飲み方のアドバイスも行っています。

なんだか安心できる気がするわ
まとめ
「飲み合わせ」について患者さん自身が気をつけることはとても大切です。
- 新しく薬やサプリメントを始めたとき
- 食事や生活習慣を変えたとき
- 市販薬を買おうと思ったとき
そんなときは、 ぜひ薬剤師に気軽に相談 してください。
「これは一緒に飲んでも大丈夫かな?」と遠慮せず聞いてもらうことで、
より安全に治療を続けられますよ。
薬剤師はその「最後のチェック役」として、皆さんのお役に立てる存在です!
また、自己判断で薬を中止・変更するのは大変危険です。
「飲み合わせが悪そうだからやめておこう」といった判断はせず、
必ず医師・薬剤師にご相談ください。

わかったぜ☆

^^;
薬剤師はその「最後のチェック役」として、皆さんのお役に立てる存在です!
—————————————-
このシリーズでは薬剤師や医療スタッフの「見えにくい仕事」を
できる限りわかりやすくお届けしています^^
他の記事もぜひ読んでみてください!
ではこのへんで。
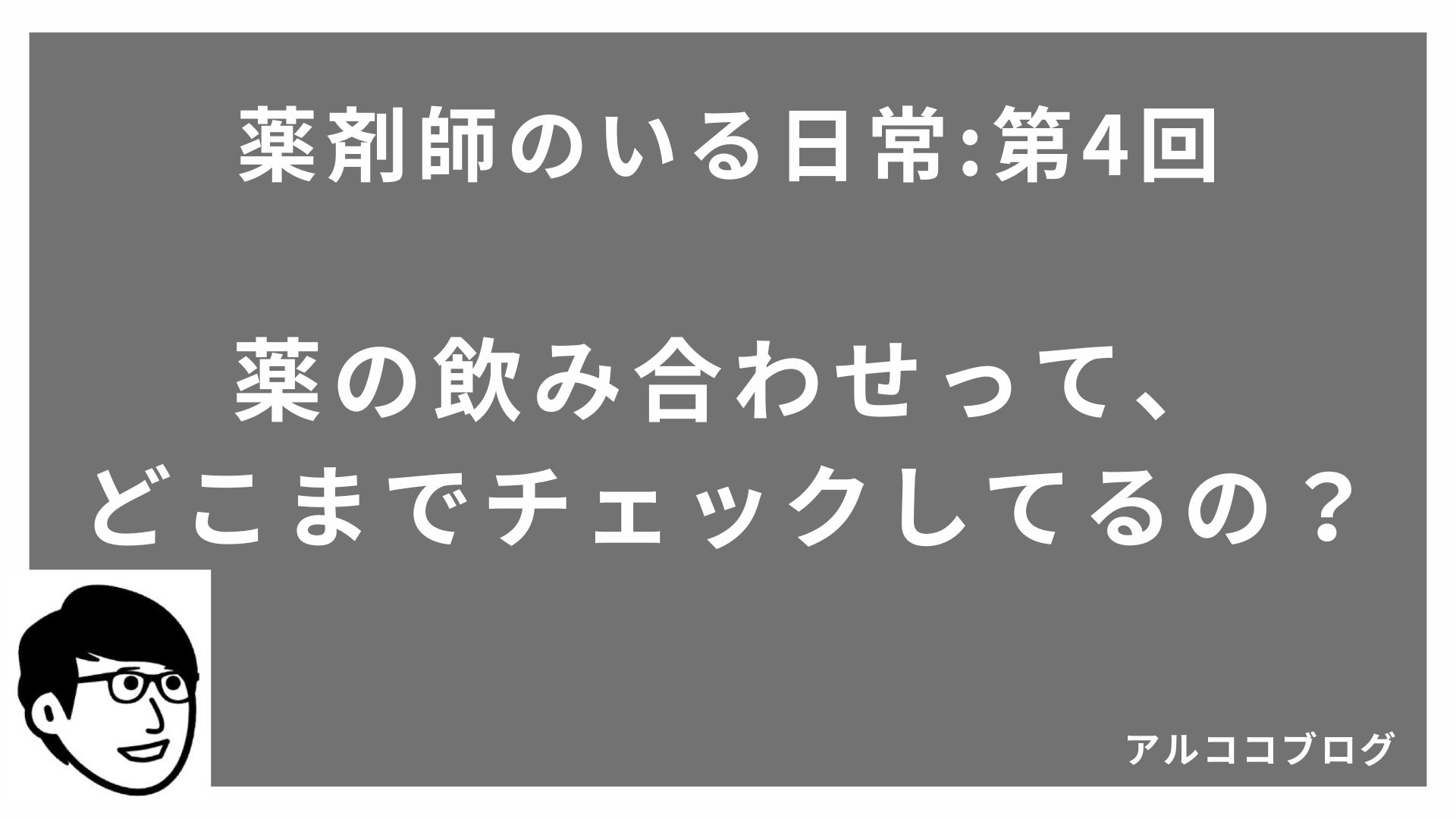

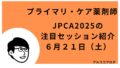
コメント