こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
今日はプライマリ・ケア研究会で計画した
多職種連携ワークショップにて、について書いていこうと思います。



雪、無音、窓辺にて!!
「にて」しかあってないよ!
今の若い子、涼宮ハ◯ヒの憂鬱知ってる人いないだろ!

^^;

orz
ワークショップのデザインの仕方も少し書きます。
なにか参考になれば幸いです^^

そんなこと言って大丈夫かよ。。。
過去に↓のような記事を書きました。
併せて御覧ください^^
なにやったの??
多職種連携ワークショップという題名で
医師をはじめとした医療職、学生(医薬看)で「連携」について考えました。
医療における連携は当たり前に必要としていても、
実際にどこまでてきているのか、できていないのか、できない理由は??
それはどうしたら出来るようになるのか、というグループワークです。
非常に難しい主題であったので
どこまで理解してもらえるか、場のデザインが重要だと思いました。
そして、県内で行われるプライマリ・ケア研究会では
こういった多職種ワークショップが初の試みでした。
私が思う連携に必要なこととして
「相手を知ること」だと思っています。
それは相手の「仕事内容」「考えかた」「大事にしていること」「好きなこと」
それらを知らずして、連携には繋がらないと思っています。
今回のワークショップでも、相手を知ることを
主題としてデザインしました。
内容を詳しく書くと、身バレするので笑
facebookで私を知っている方はそちらを見てください笑

知らんから、リンク貼ってよ

いや、ごめん。貼れない。。
場のデザイン
このようなワークショップで大事な事は何でしょうか
間違いなく、場のデザインだとおもっています。
話し合いがしやすい場を作ること、それができないと
話が進みません。
話やすい場には様々な因子が関わります。
例えば
・机の配置や部屋の環境設定
・天候等の気象条件
・参加者の班分け
・スタッフの技量(進行、スライドデザイン 等)
・そもそもの内容
・参加者事前評価
他にもありますが、上記の内容かなと思っています。
その中で私は一番、参加者事前評価が大事になってくると思っています。
活用できるのがこの本です↓
この本では研修評価について書いてあります。
評価について学ぶ方にはとても良いと思っています。
そして、どのように問いかければ、身のある内容になるかについて
この本が参考になります↓

アフィリエイトブログかよ!!

作者も自分で買っているから大丈夫だよ^^

いや、しらんけど。。
戯言は抜きにして、どちらも名著なので
手にとって見てください^^
さて、本題に入りますが
参加者事前評価をせずにワークショップをデザインすると
どのようなことに陥るでしょうか??
それは細菌培養をせずに抗菌薬を使用する良くない医療現場と同じで
相手を全く知らないので、求める内容にフォーカスできないということです。
例えば、今回のワークショップでは「連携」について話し合う内容を作りました。
参加者が「連携」についてどこまで知っているのかわからないと
概念から説明する必要があるのか、本題に入ってよいのか
わかりませんよね。
ただ注意が必要なのは、参加者評価をして、
一番理解度が低い(経験が不足している 等)と思う方に内容をフォーカスすると
理解度が高い方の、満足度が下がるということです。
「あっちをたてればこっちが立たず」となりますよね。難しいです。
理解度を事前に上げるにはどの様な仕事が必要でしょうか??
事前配布資料などで、勉強してきてということが解決策の一つかもしれません。
まぁ必ず勉強してくるなんてはわからないので
そこも未知数なんですがね^^;
このように事前評価が成功したとしても
スッタフの技量が低いと、満足度が低くなるし
天候が悪く、参加する意欲を奪うというものでも、満足度を下げる要因となってしまいます。
そしていちばん大事なのは
こちらが「提供したい内容」をどのように伝えるかですよね。
そのへんを総合的に考えて、進めていかなければいけません。
この辺リアルでお酒飲みながら話しませんか??笑
相手になってくれる人を募集しています!笑
まとめ

2025年1月に勉強会があるから多職種ワークショップやらない?

え?今11月ですよ^^; 準備期間少ないですね^^;

うん。まぁ僕も手伝うしさ^^

はい or YES
こんな無茶ぶりから始まって
運営メンバーを集めて、参加者を募って
なんとか形になって良かったと思いますし
運営メンバーで声掛けさせてもらった方々には感謝しかありません。
困ったときに、頼りになる関係を作っておくことも
「連携」があってこそですね。
参加者を集めるにあたって、医学生さんにお手伝いいただきました。
いくら場をしっかりデザインしても、参加者がいないと開催ができません。
医学生さんにはホント感謝しかありません。
自分一人では何もできないので、助けてもらって生きている。
そんな感謝に満ちた人生を送っていきたいですよね^^

死ぬの?



また他人の著作物で。。

・・・
ではこのへんで^^;;;
次は社会人大学院生日記2025年1月号でおあいしましょう。
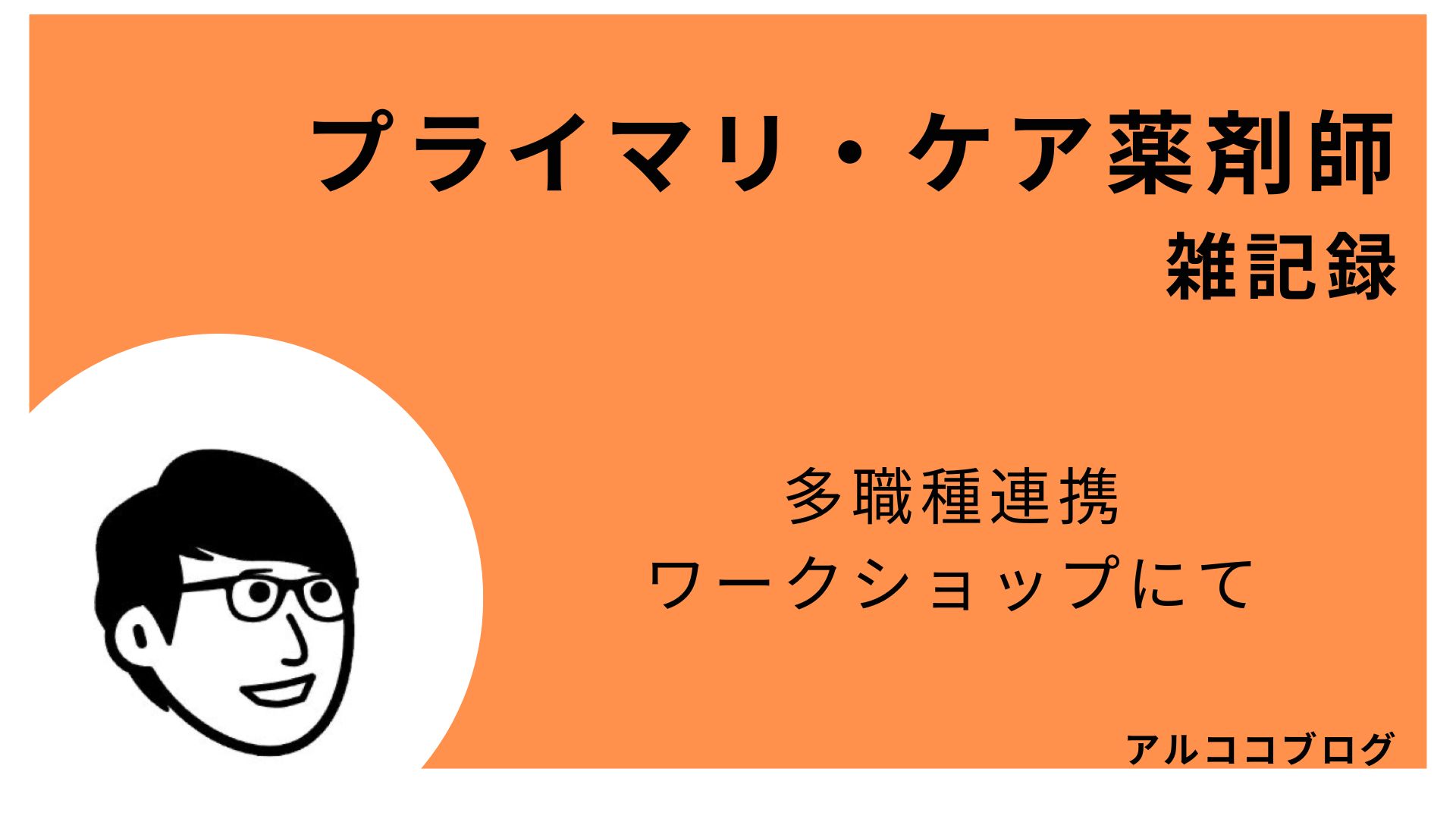
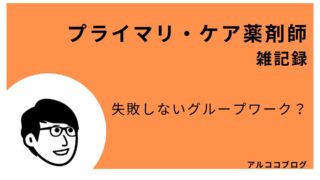

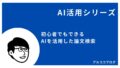
コメント