こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
社会人大学院生日記の12月号です^^
年の瀬に皆さん如何お過ごしですか。
学位論文執筆と1月のセッションの準備があって
心穏やかな年末とはなっていない作者です^^^^
さて12月のネタは「論文投稿にかかる費用」です。
ではやっていきましょう!!
論文投稿の費用??
と思った方いらっしゃいますか?
そうなんです。
お金がかかるんですよ。
「投稿費」や「掲載費」と言うものですね。
投稿費については基本的に無料のところが多いと思いますが
掲載費はそのジャーナルによって変わってきます。
当たり前ですが、高額になるところもありますね。
購読型、オープンアクセスのいずれにおいても、論文の投稿自体は無料のケースが主流ですが事務手数料を取るジャーナルも存在します。例えば、The Journal of Neuroscienceの場合は140ドルで、ほとんどの場合は50ドルから150ドル程度です。著者からするとリジェクトのリスクがあるのに手数料を取られるとなると投稿のハードルが高くなりますが、ジャーナル側からすると、査読する論文を厳選することで、作業負担の軽減やインパクトの向上にもつなげられる、というメリットがあるでしょう。
引用HP:https://kw.maruzen.co.jp/kousei-honyaku/blog/article-3.html
※2024年12月29日 22時時点の情報

1ドルが150円として2万円??

作者の小遣いなくなるじゃん。

バラすなよ。。。
このように、基本的に無料かと思っていたら投稿手数料を取るところもあります。
もう一つ大学院生になって学んだことが、
APC(投稿手数料)というものです。
APC(Article Processing Charge)
投稿手数料ですね。
ACPではありません。
こちらの書籍、本当に素晴らしいですよね^^

名著なら、ネタに使うなよ。。
APCについては、私もそこまで詳しく知らなかったので
先ほど引用したHPから持ってきました。
伝統的なジャーナルの多くは定期購読者の支払う購読料や学会の会費で成立しているため著者の側での支払いの必要はありませんでしたが、オンラインで誰もが閲覧できるオープンアクセス・ジャーナルの場合、読者からの収入がありません。そのため、著者に掲載料(APC=Article Processing Charge=掲載手数料、論文処理料などともいわれます)を課金して成り立つジャーナルも少なからず存在します。もちろんすべてのオープンアクセス・ジャーナルへついて掲載料が発生するわけではなく、研究機関や学会が費用を負担することで、著者、読者ともに金銭的な負担がないケースもあります。
引用HP:https://kw.maruzen.co.jp/kousei-honyaku/blog/article-3.html
※2024年12月29日 22時時点の情報
なるほどですよね。
読者目線からはオープンアクセスが良いなと思っていましたが
掲載料でそれが成り立っていたと言うことですね。
勉強になります。
「投稿する側」に立ってみないと、本当の意味での
「批判的吟味」なんてできないよなと学んでいます。

数本しか投稿したこと無い作者でも、
論文投稿したこと無いやつは批判的吟味するなやとか言っちゃう?

数本しか投稿したことがないから、こういう小さいこと思っちゃんじゃないか?

なるほど。
戯言は置いておいて、結局のところAPCはいくらかかるのか
具体的な話になりますが
APCはいくら?
またまた引用しますね^^

適当なこと言うより全然良いやろ。
オープンアクセス・ジャーナルの掲載手数料は、ジャーナルによってまちまちです。一般的にインパクトの高いジャーナルほど高額になる傾向がみられるとされますが、例えば、Elsevierでは掲載手数料に関するポリシーとして、ジャーナルの質、編集工程、他誌の価格、市場の状況、ジャーナルが手数料以外から得ている収入などを鑑みてそれぞれに決めるとし、実際に数百ドルから5900ドル程度の幅で設定されています。(Cellの5900ドルが最高額。参考:https://www.elsevier.com/about/policies/pricing ) Wiley、Springerなどでもそれぞれの刊行する雑誌の掲載手数料のリストが見られます。 掲載手数料については、必ずしもすべての著者に一律で同じ金額が課せられるわけではなく、発展途上国の研究者が発表する論文については手数料を無料にしたり減額したりする 出版社もあります。
(参考: https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/for-authors/waivers-and-discounts.html)引用HP:https://kw.maruzen.co.jp/kousei-honyaku/blog/article-3.html
※2024年12月29日 22時時点の情報

5900ドル???

885,000円!!!!!!!!!

やっば!
私はCellという雑誌を読んだことがありませんが、凄まじいですね。
びっくりしました。
投稿しようとしている論文のAPCは確認しないとだめですね。
ちなみに
PC連合学会の和文(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/generalist/-char/ja/)は投稿費もAPCもかかりません。
査読もしっかりしているので、私はかなり勉強になりました。
このAPCはImpact Factorが高い雑誌ほど、高くなる傾向もあるようです。
ここでImpact Factorとはという話になりますが
インパクトファクターは、引用された数÷論文数で求められます。特定の期間において、ある雑誌に掲載された論文が 平均的にどれくらい頻繁に引用されているかを示す尺度で、雑誌の影響(インパクト)を表す指標の一つです。同分野の他の雑誌と、その影響を相対的に比較できます。
まぁ名前のとおりではありますが
影響力というものですよね。
ここで私が常に思う疑問なんですが
Impact Factorは高い方が良いの?
という話です。
論文をよく投稿される先生方は
IFの高い雑誌にアクセプトされました!
とSNSに書いていること目にしますが
個人的な意見としては、必ずしもIFが高い雑誌が良いかと言われると
そうではないなと思っています。
一般論として
英文より、和文のほうが難易度が低いのかもしれませんが
私の経験ですが和文をacceptされるというのはかなり大変でした。
そしてPC学会の和文誌(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/generalist/-char/ja/)は、査読がかなーーーーりしっかりしているので
私はメタメタにご指摘いただきました。

それは作者の研究デザインがメタメタだったからでは??

そうだよ!!!
ということで
「論文を通す」という経験は
IFが高い雑誌でなくても経験できることであり
初学者の先生方(や私は)は肩肘張らずに
投稿するという目標、acceptされるという目標を達成できる
投稿先を見つけると良いと思います。
ここで一つ誤解をしてほしくないのは
IFが高い雑誌に作者自身も掲載されてみたいと言う願望はあります。
影響力があるところに、掲載されるという経験はしてみたいですからね。
作者が投稿する雑誌は?
学位論文のことなので、大っぴらには言えませんし
ましてや形にもなっていないので
目標としている投稿先を述べることも適切ではないかなと思っています。
大学の学位規定には
IFが高いところという具体的な記載はありません(例えば2以上)。
とりあえず、英文でAcceptできればよいということで
上に書いたように肩肘張らずに、頑張れるところを探しています。
社会医学系雑誌で良いところがあれば教えて下さい。。笑
ちなみにこの費用に関しては
所属している教室が払ってくれることが一般的です。
一度教授と相談ですね^^^
まとめ
2年生も終わりに近づいて来ると
学位論文の話が出てきて
少しずつですが、博士に着実に進んでいるんだなと思っています。

研究ポシャった話は?

それは9〜11月号でかいたよ!!財団の研究費落ちたからね!!

今は何やってんの??

既存のデータの解析で新たな視点から統計的有意差を出そうとしている。

それもおもろいな。

個人的には統計を勉強できていて楽しい。
多重ロジスティック回帰分析を自分でやるなんて思っていなかった。

来年はrejectされないように、一度投稿してみたいと思います。
まずは2月の中間発表会までに原案を作ることから、、、
先日、久々に会った本院の後輩(薬学博士)にこの話をしたら
「2年生で論文書き始めるって、最高っすね。もう博士取れましたね^^」
と言っていました。
彼は基礎研究をしていて、地震とかいろいろな理由から3年生の後半で一度ポシャったそうです。
それと比べれば、かなり順調と言えるのかもしれませんね。
というかこういう実際の経験の共有って
シンポジウムで面白いと思うんだけどな。。
なんてね。
今日はこのへんで。。。
ご挨拶
2024年もアルココブログに御アクセスいただきありがとうございました。
こんなブログですが、皆さんに見ていただけることがかなり励みになっています。
私はブログを通して
文章を書くスキルを得られている(と自負している)。
大学院に進学したい人の背中を陰ながら押せている、と思っています。
2025年も無理のない程度に更新していきます。
今後とも末永くよろしくお願いいたします。
アルココブログ 作者 拝
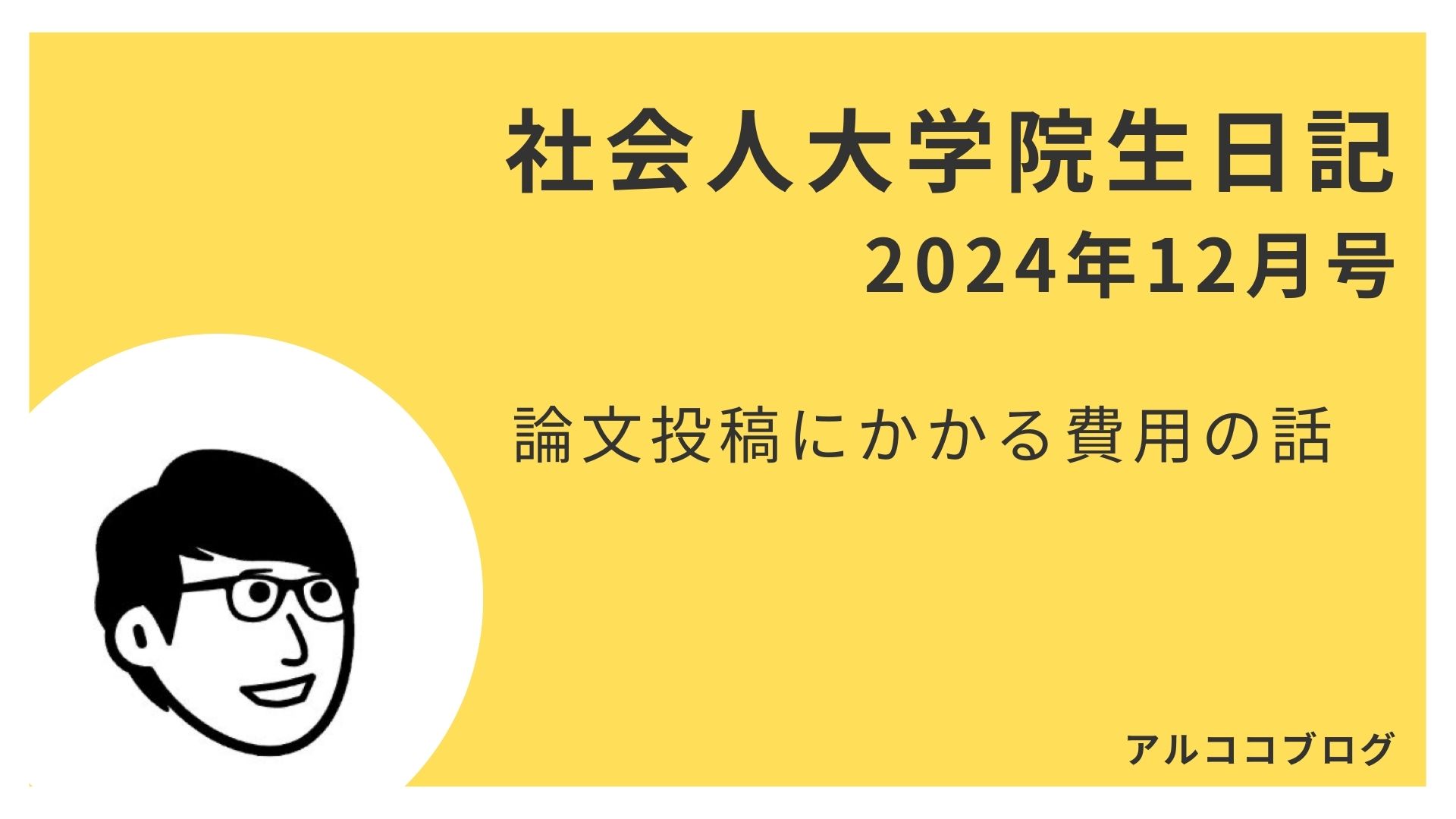



コメント