おはようございます^^
いつもアルココ(薬剤師)のブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、何かと話題のFaculty Development(FD)について書きたいとおもいます。
アルココは岡田唯男先生が代表を務めるHANDS-FDFの卒業生であります。
そのため「多少」はFaculty Developmentについて知識があります。

知識があるなんて言って大丈夫なのかよ・・・
思いっきり中の人がバレそうなネタですが
みなさんと一緒に勉強できたらと思っています。
そもそもFDって何?
まずはFDについてですが
Faculty Developmentの頭文字です。
教員が、授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な取組の総称
https://www.aoyama.ac.jp/outline/effort/fd/
大体どこのHPを検索しても、上記のような定義が出てきます。
「教員が」となっていますが、決して教員でなくても必要な取り組みです。
組織力向上のため、個人がレベルアップする勉強とお考えください。
皆さんが日頃行っている「薬剤師業務」は
大学で6年間(4年間)学んできた知識だけでこなせますか??
いやいや無理だよって思いませんか?
例えば、
・休みをもらうための交渉。
・先輩を含んでチームをやるときにそのリーダーに選出された。
・難しい患者対応。
などなど
あるあるではないですか?こういう内容は残念ながら薬学教育では学べないんです。
「ビジネススキル」とお考えください。
こういった勉強について、私は必要だと思っています。
このFDの知識を薬剤師の業務に適用することで
薬剤師としての専門性やサービスの質を高めることが期待できます。
そのために色々学ぶわけですね。
Faculty Developmentと言いながらも
何を学ぶかふわっとしていると思いますが
その一例がこちらです。
項目が何個か羅列されており
なんとなくわかりましたでしょうか?
どの様に勉強する?
多分読んでいただいている皆さんの頭の中は
→ FDをざっくり理解した。
→ 学ぶべき項目もなんとなくわかった。
→ 薬剤師業務に必要だともわかった。
このあたりかと思います。
そして、大学教員ではない薬剤師の皆さんは
どうやって学ぼうかと思っているのではないでしょうか?
①公式なFDプログラムや研修に参加する。
・岡田先生が行っているHANDS-FDF
・暖簾分けされた地方HANDS
・プライマリ・ケア学会や他学会主催のFD研修会
・大学で行っているFDプログラム
上記のHANDSは医師だけではなく、薬剤師も参加可能となっています。
PC学会のFD研修会は今後も続いていくのでしょうか?
単発で終わらないことが必要ですよね。
②専門的な書籍から学ぶ
・独学でそれぞれの書籍を勉強する
時間はかかりますが、費用の面から見ても一番始めやすいかもしれません。
③オンラインリソースを活用する
他は知らないのですが。。
udemyですと、faculty developmentという単元はないのですが
ビジネススキルを学ぶことが出来ます。
1単元から購入できること、自分のペースで学習できることで、
FDとは関係ありませんが私はTOEIC動画を聞きながら通勤しています。
たまにセールをやっているので、そこで購入することがお得です。
チェックしてみてください^^

案件?
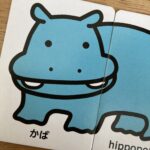
だといいんだけどね。。
④HANDS卒業生に講師を依頼する
これは①に通じるものですが
HANDSの卒業生は結構います。
私もその一人ですが
研修会を開いてもらうように交渉すると良いと思います。
講師も反転学習となります。
ちなみに以前、オンラインで行っているPC薬剤師勉強会で
FDを取り上げ、Difficult learning encounter(DLE)を学びました。
平日の21時半から23時まで行っていました。
あたおかですね^^
上記①〜④でもし興味があるものがあれば、チェックしてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか
FDの取っ掛かりとして
かなり端折って書きました。
興味を持っていただければ、各項目を解説していきたいと思います。
何かあればコメントをお願いいたいます!



コメント