先日看護師さんむけに行った内容を図解でも使用しています。

使いまわし。。
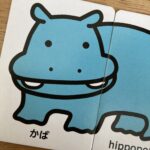
・・・
なにはともあれ、褥瘡治療に関わりたいと思っている薬剤師や看護師さん
介護スタッフの皆さんのなにかお役に立てれば幸いです。
では行ってみましょう
褥瘡を考える時

これはわたしの経験になります。
褥瘡を学び始めると
「創を評価してください」が一番先に出てくるんですよね
分かるわけないですよね?←
何も学んでいない状況で、この創をみて軟膏をとか、デブリとか、ズレているとか
わからないんです。
そのため、最初から嫌になってしまうんです。
そして、ドレッシング材は知らないし、軟膏の基剤もあんまり詳しく知らないしで
わたしは嫌になりました!
そこで考えたのがこちら。

実際に使用している軟膏を知ることで、今の創の状態を推測できるのでは?
という形で勉強し始めました。
やはり基剤は大事
基剤は軟膏の何%か分かりますか?
95%なんですよ、ほぼですよね?
ということはその基剤を理解してあげないと武器として使えないわけです。
そこでこのスライド

われながら、文字が多くて嫌になりますが、一応かいつまんで書いてはいます。
この内容は口頭でも看護師さんに伝えたのですが
一番ペンが止まった感じがしました。
「文字ばっかりのスライドは見ていて嫌になる」を再確認しました。
話したことのまとめ①
実際に基剤、使用方法、薬効など記載したものがこちらになります。

この表の見方は
例えば「殺菌」の軟膏を選ぶ時
創部環境がどうなっているかで選択していきます。
ゲーベン®を使っているのであれば、
創部が乾燥していて、感染しているような創に使用しているんだなぁ
と言うふうに推測できるわけですね。
実際にそれを観察して、どうなっているか知識を得ていくと良いと思います
わたしの知識レベルは実際に観察して、WOCNsに様々ご教授いただいて
覚えている最中です・・・
まとめ

また知らない単語が急に出ましたが
黒色期、黄色期、赤色期、白色期 と褥瘡が良くなっていく経過ですね。
黒色期の写真を見ると、乾燥してカサついてますよね。
そういうところには補水作用がある軟膏がよくて
黄色期になってくると少しジュクジュクするので、
まだ殺菌を求めているなら吸水作用があるイソジン®シュガーパスタなどを使用する
と言うように
一般論をスライドに載せたものになります。
別な使用方法もあると思いますので、あくまで参考程度に。。
最後に
薬剤師が褥瘡回診に入って一番大事だと思うことは
体位交換の手伝いをしましょう!
軟膏がわからなくても、何しているかわからなくても
褥瘡の処置で体位交換をするときは、絶対に人手が必要ですよ!
積極的にやっていきましょう!
今日はこのへんで
ここまでご覧いただきありがとうございました。
間違いはぜひぜひご指摘ください。
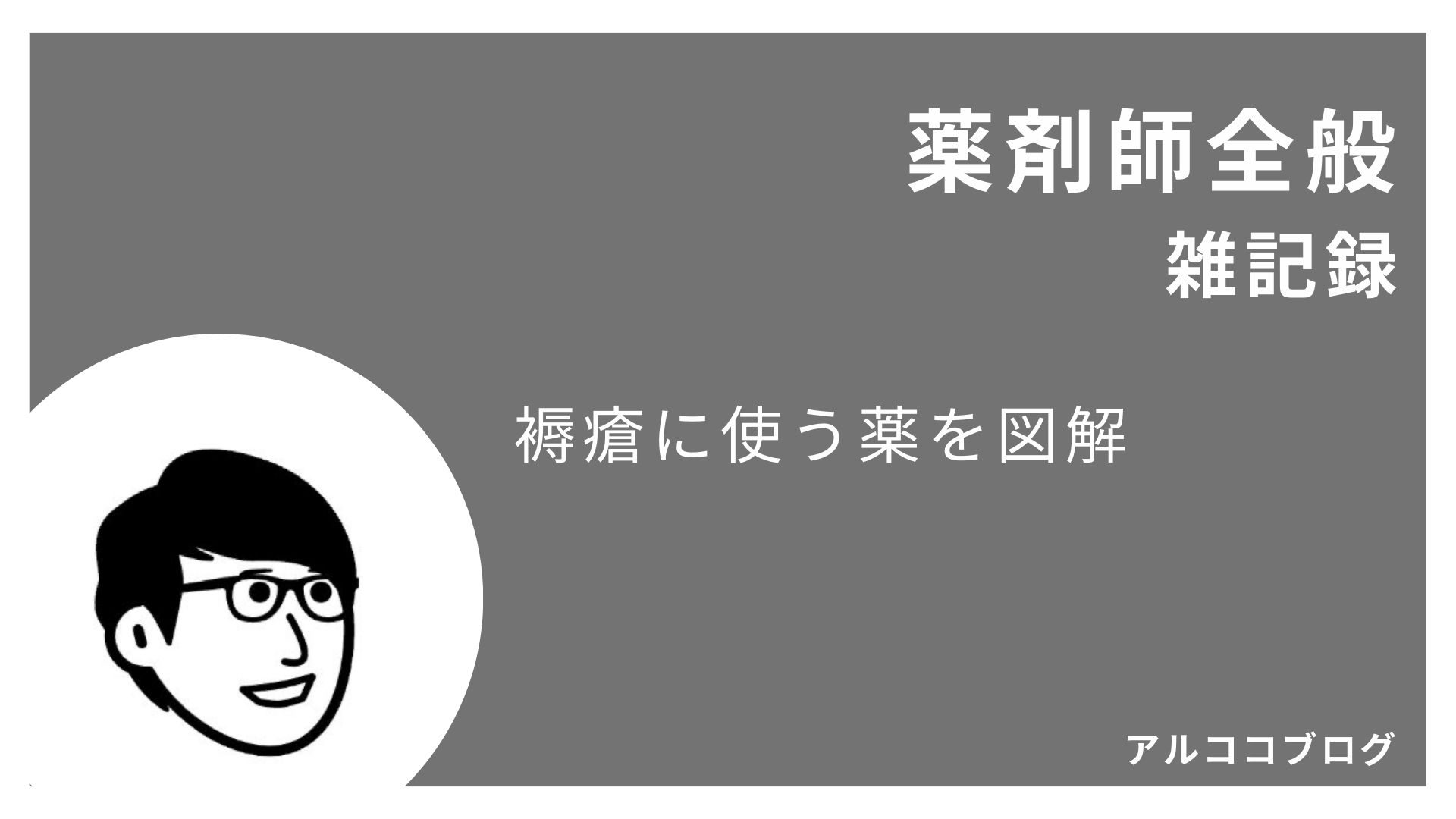
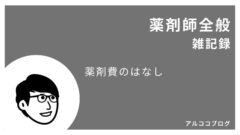
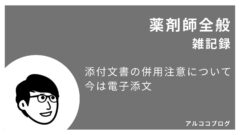
コメント