経静脈栄養設計の図解解説になります。
よかったら見ていってください。
表紙
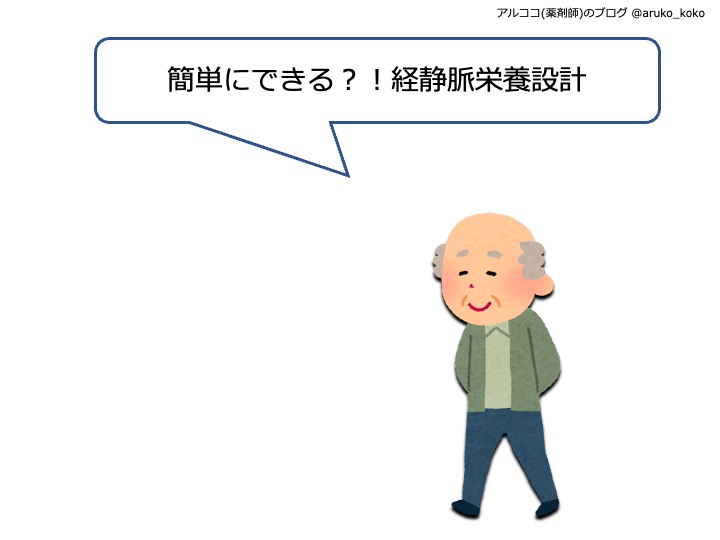

このおじいさん影があるね。
本編とは全く関係ありませんが、おじいさんに影をつけて良い感じにしました。
仮設定
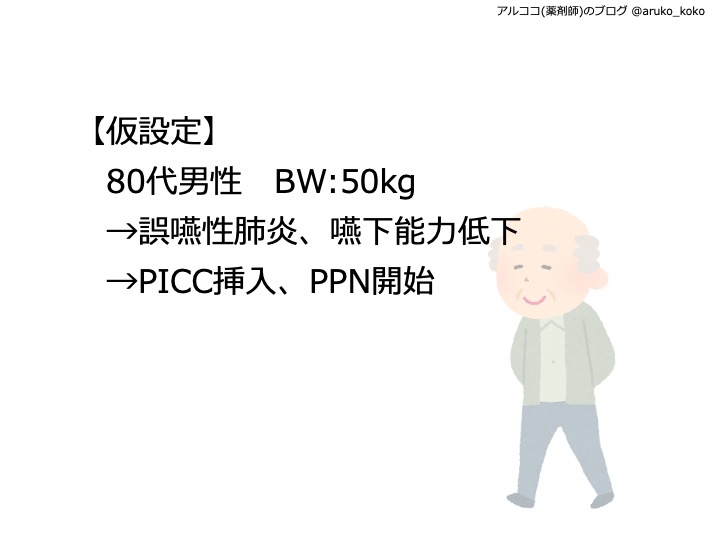
市中病院などでよく見る症例では無いでしょうか。
当院ではCVポートの造設よりも、PICC挿入が多くなりました。
保険点数上もPICCのほうが安かった記憶があるので、加味されていそうですね。
この症例は
背景がpoorなら、総合診療科が診ることになりそうです。
誤嚥性肺炎で入院した後、嚥下チームにて嚥下能力を評価したものの
経口摂取が難しいとなることもしばしばですね。
栄養と関係ありませんが、誤嚥性肺炎となると「ユナシン®」と盲目的に言いたくなります。
きちんとDe-escalationするように喀痰培養、レントゲンなどを精査したいですね。
簡易式からの1日必要量を設定
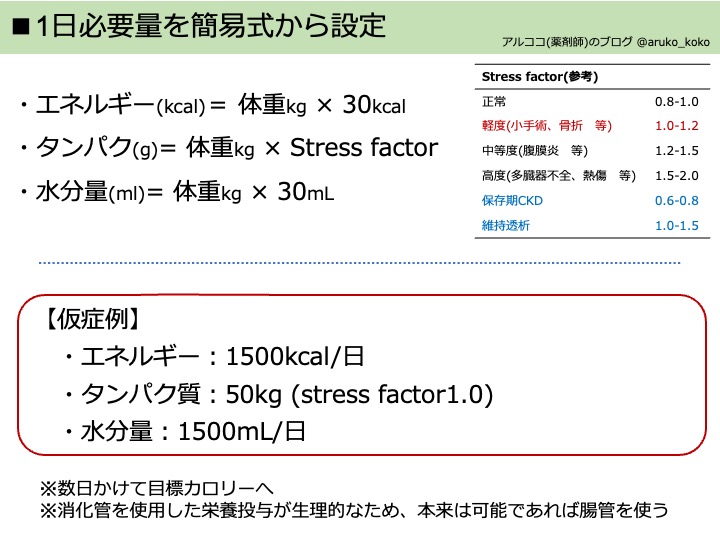
この図解で一番伝えたかったことになります。
栄養は簡単に考えないといけません!
カロリーの設定を行う際に
ハリスベネディクトの式から設定するとなると
あの式を見ただけで嫌になりますね。
そういうときに、ざっとで良いので簡易式を用いると楽にスタートできます。
肝機能が悪くなってきたら、栄養が多かったかな?
栄養指標(プレアルブミン、Albなど)が改善しないは、栄養が少なかったかな?
のように経過、検査値を見つつ補っていけばよいのです。
次がタンパク質ですが
必ず入れることを考えましょう。
保存期CKDならば減量します→0.6g〜0.8g/kg
透析ならば→1.0g/kg〜1.5g/kg
透析に移行した患者で、保存期CKDのままタンパク質が少なく入っていることが散見されます。
タンパク質量の増量を提案しましょう!
体を作るにはタンパク質が必要です。
腎機能が問題ないならば「病態を考慮してタンパク質量を決定します。」
最後に水分量ですが、こちらも病態を考慮して
心不全や、肺疾患がある場合、水分量は減量した良いかもしれません。
仮症例で設定した値は赤い箱の中に書いていますが、誤植がありました
タンパク質:50kg→50gです。。。
処方例とチェックポイント
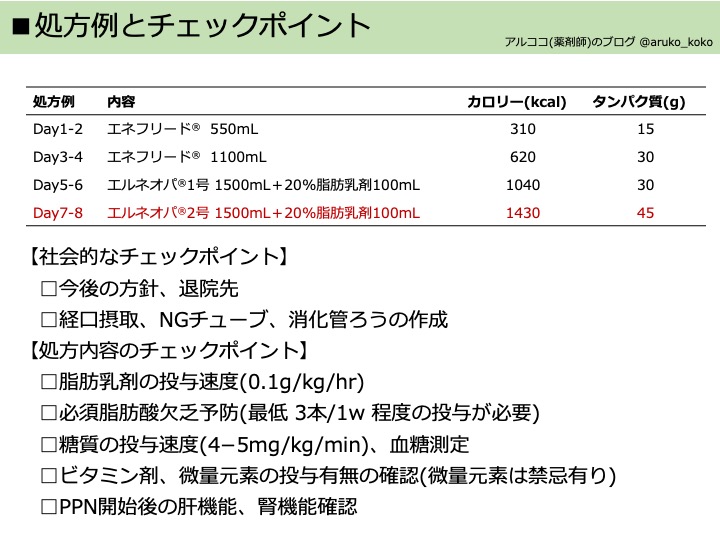
当院では最近エネフリード®を採用したのですが、結構よく出ます。
脂肪乳剤も入っているので、ちょっと面倒になったビーフリード®と思ってもらうと良いかもです。
目標のカロリーには数日かけて持っていきましょう
検査値、経過をフォローしつつ
チェックポイントを確認します。
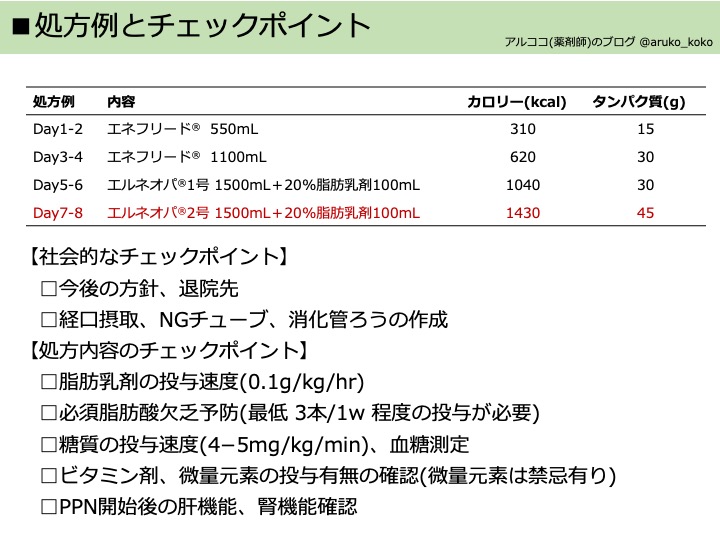
・社会的チェックポイント
今後TPNのまま行くのか、経腸栄養剤をNGチューブもしくは消化管ろうを作成して
経腸栄養剤を投与することになるのか、そこは確実に確認していく必要があります。
退院先、転院先も含めて医師の考えを確認しましょう。
・処方のチェックポイント
続いて脂肪乳剤を入れるか入れないかですが
感染している人に投与しにくいという文献があるので、アップデートされていなければ
考慮したほうが良いですね。
禁忌項目に該当しないならば、速度を守って1g/kgで入れると良いです。
脂肪乳剤の投与速度が早い場合は TG が上昇してきます。
それ以外のチェックポイントは当たり前ですが
糖質の投与速度はなかなか知らなかったりするので、体重が40kgとか軽い方に
1日に高カロリー輸液が2本という処方が出たら必ず確認します。
まとめ
まとめますと
①必要栄養量、水分量を決める;簡易式が簡便
②腎機能をみてタンパク質量を決める
③脂肪投与を決める、投与可能ならばg/kg
※最低週3回投与で必須脂肪酸の欠乏を防げます。
④必要栄養量からタンパク質、脂質のカロリーを引いたものを糖質で補う。
⑤微量元素、ビタミンを忘れずに!
⑥検査値、経過、今後の方針を確認。
結構簡単でしょ?

説明ざつ。。。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
では失礼します。
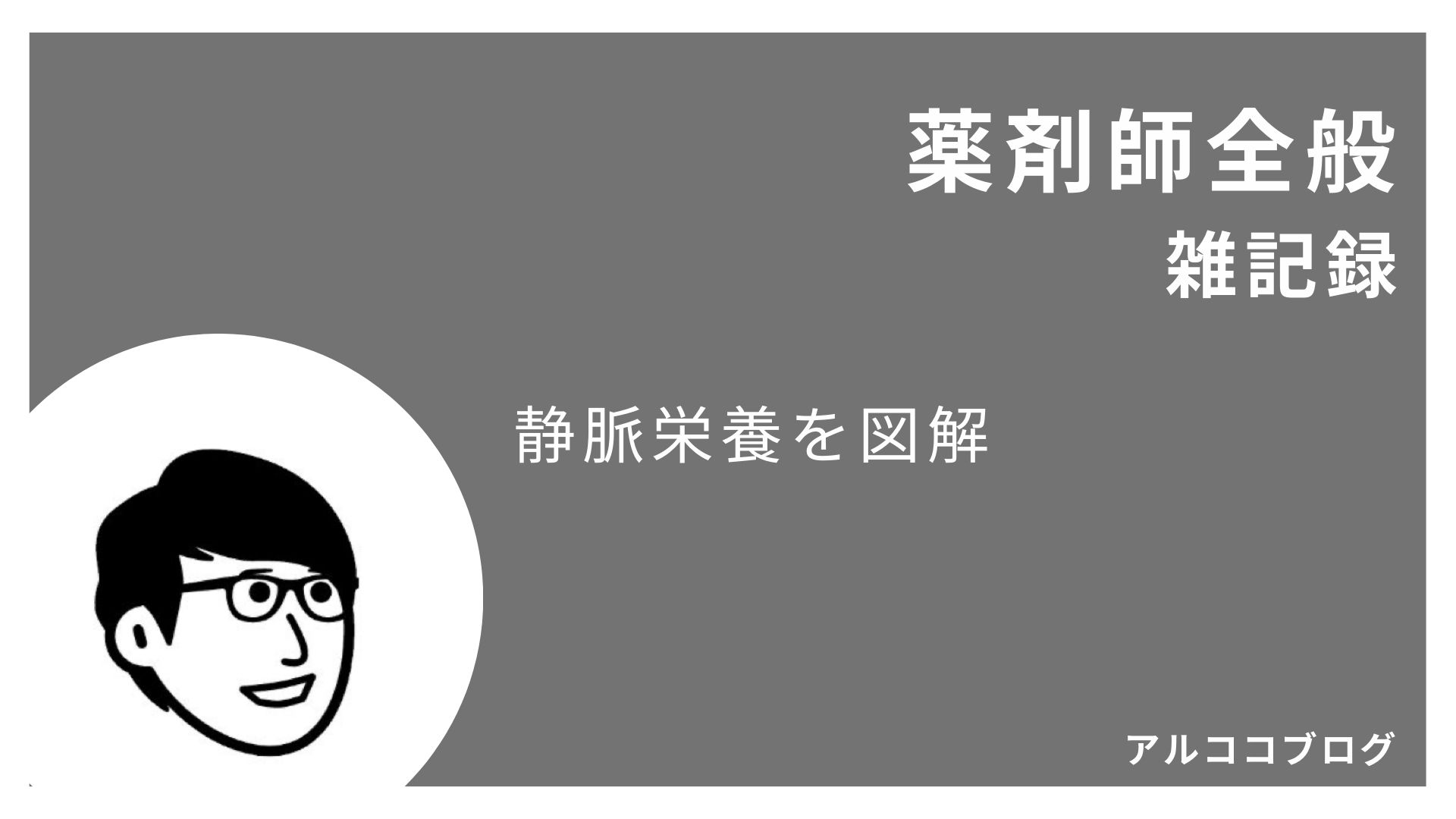
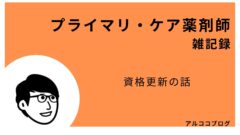
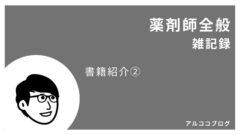
コメント