こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
社会人大学院生日記の2月・3月号です。
今月号は2023年度のまとめになるので2024年度に向けた「研究の話」です。
少し振り返りも含みますが、最後までよろしくお願いします。
一年間の振り返りはこちら↓
過去の大学院ブログはこちら↓
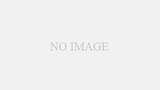
社会人大学院生の経験を書いています。
2023年度の話
2023年度は無事に終了しそうです(あと2日)。
研究を行うに当たり、指導教官と密にdisccusionを行ってきました。
現在に至るまでの経過を振り返ります。
2023年4月の話:最初のプレゼン
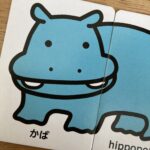
ポリファーマシーの研究をしたい。
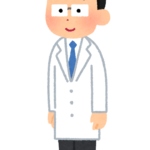
おk。 文献見て、明らかになっていないこと見つけとけ。
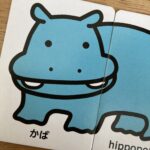
PubMedの検索式をChatGPTに作ってもらおう

御意。
【番外編】ChatGPTにPubMedの式を作ってもらう方法。
「PubMedで〇〇についての文献を探す検索式を作ってください。」
と打ち込むだけです笑
PubMedだけではなくWeb of Scienceでも依頼が可能です。
ChatGPTの書籍を見ていると、「あなたは〇〇の専門家です。」と役割を設定したほうが良いようです。
それを検索するだけです。
ある程度精度が良いですが、Hitした文献の精査は絶対に必要です。
ポリファーマシーで検索しているのに
全く違う文献が組み込まれたりすることもあります。
※注意点※
過去に、ChatGPTが作った式をぶち込んで検索した時
全く論文がHitしなかった時があります。
多分検索式が良くなかったんです。
こういうことも稀にありますし
なぜか中国の文献だけ引っかかることもあり
網羅的に拾えていない可能性もあります。
なので、Hitした文献の精査は絶対に必要です。
【番外編】論文の読み方(アルココの場合)
大学院生が教えてあげますよ^^^^^^^^
上の検索式でHitした文献を読んでいきます。
一つの論文をしっかり読むのであれば
PICOにまとめるとかappendixまで読むとかありますが
多くの文献をざっと読むので、
Background、Methods、Discussion
あたりを重点的に読みます。
Backgroundの最後辺りに、「〇〇が明らかになっていないので、調査した」ってのありますよね。
この辺はしっかり読むとよいです。
過去の文献を、調査したうえで書いている(はず)なので
文献の周囲情報も分かりますね。
あとは皆さんご存知のMethodsとDiscussionですね。
個人的にはlimitationのところは特に気にして読みます。

わりとあたりまえやん。
かなり脱線しましたが
こんな感じで文献を漁っていたところ
ポリファーマシーの研究について少し雲行きが怪しくなってきました。
2023年6月の話:Hitした文献の精査、まとめ
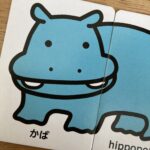
Positiveな結果の文献が少ない。なにより、結果が出尽くした感じがする。
そうなんです。
私が調べた限りでは、ポリファーマシーの解消によって
良い結果につながることがあまりないんです。
経済的には良くなりますし、相互作用も減ります。
そりゃ薬を減らせばそうなる、って感じですよね。
こんな感じで、見た文献で調べようとした結果が
似通っており、新規性を求め辛い感じがありました。
そこで
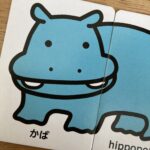
ポリファーマシー解消後の心理状態を調査できないか?
と思いました。
心理面にアプローチした研究が無く(少なく)、これは新規性が出るかなと思いました。
指導教官にプレゼンしたところ
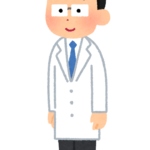
おk。実施計画書書いてみてや。
うちの指導教官は学生の言う事をそこまで否定しません。
2023年6月以降実施計画書を書き始めて難航し始めたころ
自分にとってはびっくりしたことが有りました。
2023年7月ころの話:研究の変更
指導教官から
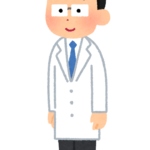
予防に関係した研究をしないか?
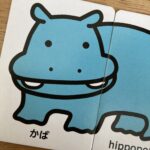
え?あれ?ポリファーマシー解消は?
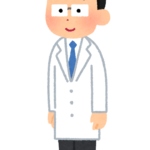
それはそれで副論くらいにして、こっちを主論にしよう。
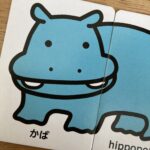
主論?副論?

主論文(primary article)とは、オリジナルの研究や実験、観察に基づいて書かれた論文のことを指します。副論文(secondary article)は、既に公表されている研究をまとめたり解釈したりする論文です。
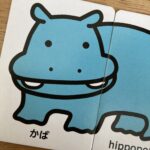
なんだか指導教官の言っていることと若干違うような?
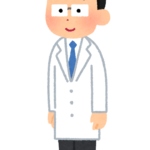
やるの?やらないの?
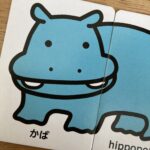
もちろんやります
研究テーマ変更!!!
こんな事日常茶飯事ですよね^^^^
本当に研究を開始する前で良かった。
実施計画書を作成し、倫理委員会を通して
研究開始していたら、どうしようって感じでした^^^
2023年8月〜12月:予防に関する文献の調査
指導教官の言う「予防の研究」は
まだまだエビデンスが限られており、これからと言う領域でした。
※どの分野の予防かはご想像にお任せします^^
ポリファーマシーの研究と同様に
式を作ってもらい、文献を読み耽ることにしました。
その中からなんとなく課題が見えてきて
薬剤師が「予防」の研究を行う意義ってのもなんとなく見えてきました。
我々薬剤師は、患者を相手にしますが
患者になる前の人に
「患者にならないようにしましょう」という仕事は
日常業務の中でそこまで経験がありません。
患者に対して、悪化しないように、生活を整えましょうはありますがね。
という計画を
2023年9月から開始し
2023年12月にようやっと実施計画書第一版が整いました。
時間がかったのは私がだめ学生だからです^^^
【番外編】nの稼ぎ方
2023年10月くらいにふと気づいたのですが
今後前向きの研究を行う予定であり、患者数を稼がないといけません。
入院患者を対象にするのか、外来患者を対象にするのかでやり方は別ですが
どちらにしても医師の協力は必須です。
ただ私の場合指導教官が分院(アルココは本院)にいるため
直接的に協力を得にくい感じがありました。
所属教室の教授に依頼して見ようかと思いましたが
あまり実務に従事される先生ではないので、こちらも難しい。
では若手の先生に!と思いましたが、こちらも難航し
研究できるの???と不安になりました。
大学院に行きたい方は、指導教官がどのように研究に関わってくれるか
教室に属している他の先生が、どの程度手伝ってくれるのか
明らかにしておくと安心ですよ^^^
大学院生の本文は「研究」です。
それを最大限頑張れるように、環境を整える能力も必要です。
2024年度から
そういうこういうが有りまして
2024年度から
アルココは分院の移動が決まりました。
正直、こんなにスムーズに異動が決まったのも
部長を始めとして上司の理解があったからです。
講義を受けるための時間給の取得にも理解が有り
職場の協力が何よりありがたかったです。
しかし部長の方から

2年間だけな。人たらないから、それ以上は無理だぞ
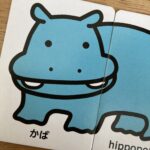
御意
と言うこともあり。
体制が薄い中での異動であることを再認識しました。
これから、社会人大学院に行く方は
上司の協力を得られるように交渉しましょう。
過去のブログにもそのあたりを書いています。
ということで
研究頑張ります^^^^^

長い話やった。。。
4月以降は研究の進捗具合
学会発表、論文投稿についてを書いていければと思っています。
今後ともアルココブログをよろしくお願いします。
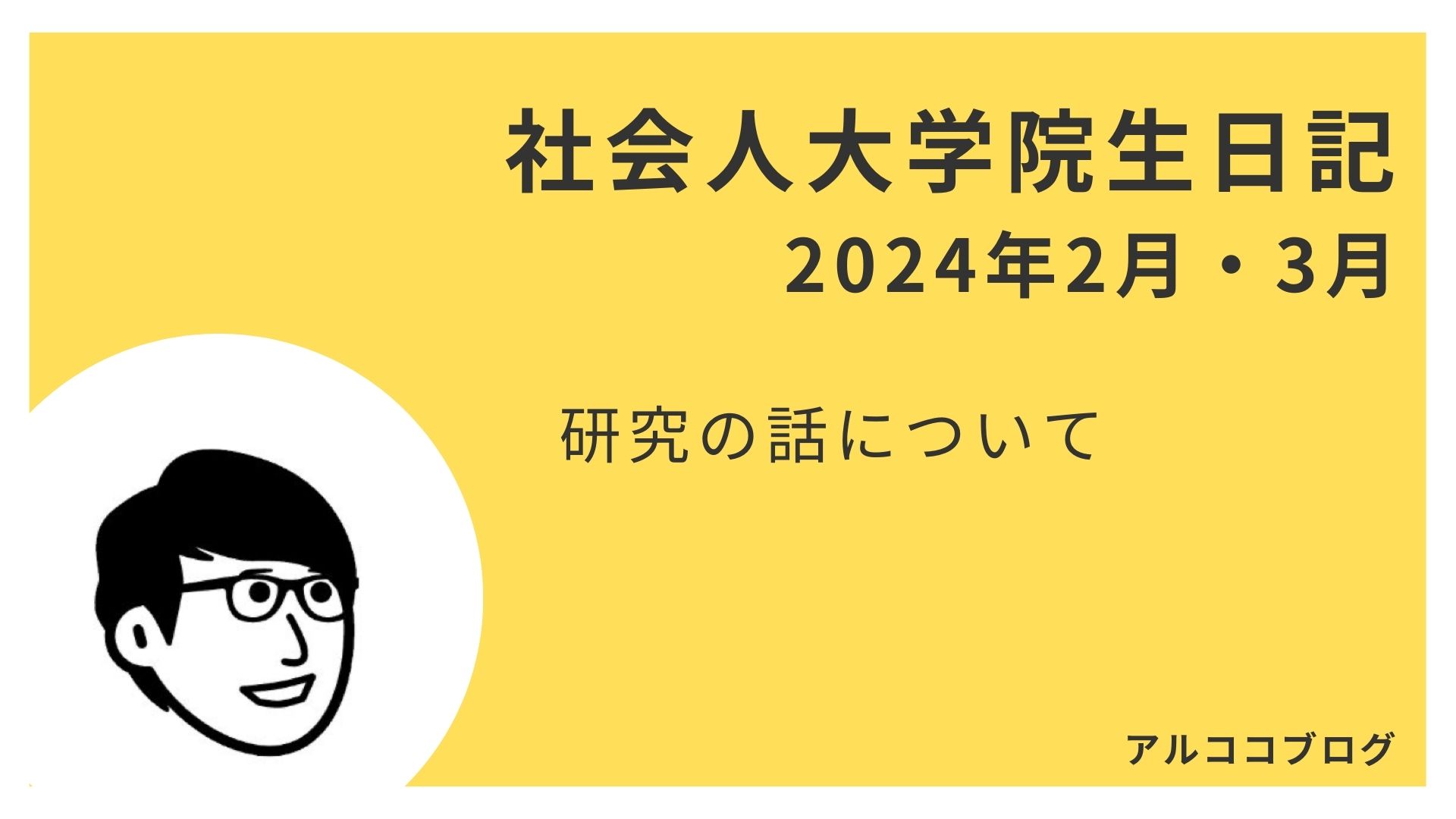

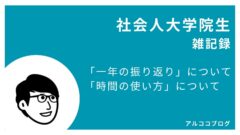

コメント