こんにちは^^
いつもアルココブログを御覧いただきありがとうございます。
今回は、大学院で学んだ内容をどのように職場で活かしているか
お話したいと思います^^^^
ではやっていきましょう!!
【講義】を職場で活かす。
まずは講義で学んだことを、職場でどのように活かしているか
現在の二年生まで学んだ科目は下記になります。
| 科目名 | 内容 |
| 生命倫理・研究倫理概論 | 研究を行う上での倫理について学ぶ |
| 研究方法概論 | 教授陣の過去の研究を学ぶ |
| 医学統計学・医学統計演習 | R、SASSの説明と演習 |
| 医学英語 | 論文の読み方を学ぶ |
| 地域医学総論 | 地域医療を学ぶ |
| 地域医学各論 | 地域医学総論で学んだ内容を、掘り下げる |
| 地域医学「特論」 | ひたすら論文読むやつ |
| 腫瘍内科学「特論」 | がんの成り立ちからゲノム、最新の治療について学ぶ |
ざっとこんな感じです。
ツッコミどころがあると思いますが、スルーしてください^^
必修がほとんどですが、表の下2つ
「特論」は選択科目でした。
「自分の教室の科目」と「好きな科目」
と言うように最低限のルールだけ決まっていて、数ある科目がある中から
好きなものを選ぶ形でした。
何なら私は薬剤師ですが
消化器外科特論や心臓血管外科特論などの「外科系」についても
履修は可能でしたが
まぁ選びませんよね^^^^^
この中でどれが一番役に立っているかと言うと
受講したすべての科目なんですが、特に
表の一番上の「生命倫理・研究倫理概論」かなと思います。
◯生命倫理・研究倫理概論
ちょっと学部時代の話を交えますが
学部時代の「倫理」は医療現場を知らないがゆえに
教科書に書いてある内容が他人事で
何を学べば良いのかわかりませんでした。

それって作者が頭悪いだけじゃね?

いやまぁ、、仰るとおりなんですけど。。
倫理の講義は「症例から検討するスタイル」でした。
教授が症例を持ってきて、ここが倫理的にどうだろうとか
どうすればよかったとか
学生(医師、NP、薬剤師)みんなで検討しました。
倫理と言っても答えが出ない問題を考えるので、様々意見が出たことで
プライマリケアに通じるものがあってかなり勉強になりました。
ここで学んだことを活かして、、倫理的な人間になりたいと思います^^^

草
◯腫瘍内科学特論
続いては、一番臨床に直結している講義の
腫瘍内科学特論です。
腫瘍内科の教授に1対1で教えてもらうという
なんとも贅沢な15コマでした。
教授の専門分野のゲノムについてや
最新の論文から、◯◯がんの標準治療を教えてくれたり^^^
講義後にケモ室で認定持ちと学んだ内容を話していました^^^^^

教授が何言ってるかわからなくて眠くなったのは内緒

!!!!!!!!
正直言うと、この腫瘍内科学特論は
基礎知識がない私が受けて良いものではなかったかもしれません。
大学病院での病棟も
消化器外科・泌尿器科がメインで、泌尿器科以外の抗がん剤をあまり触りません。
「がんゲノム」を詳しく学んだのもこの特論が初めてでした。
ということで、講義内容がさっぱりわからず眠くなったことも有りました^^^
ただ、知識のない私が
ケモ認定持ちとある程度話ができるようになったということは
この15コマのおかげだと思っています。
この経験から皆さんに言えることは
自分が学びたいと思ったときに、基礎知識はなくても大丈夫ということです。
いや極論かもしれませんが
これから学べば良いんですよね^^
確かに基礎知識があることに越したことは有りません。
私も「がんゲノム」をせめてかじってから
受講すればと思いましたが^^^
今更遅いです^^
研究から学んだことを現場で活かす。
続いては研究の話です。
下のブログがそれに関係したことです。↓
現在行おうとしている研究は
指導教官(医師)が昔から行ってきた研究になりますが
過去文献の調べ方、研究資金の調達方法
オープンデータを用いた研究
など、普通に薬剤師として臨床研究を行っても
ここまでの知識を短期間に得られなかっただろうなと思います。
実際の研究は来週の本審査に望みます!!!
まとめ
大学院で学んだことを臨床でどのように活かすか
というタイトルで書いてきましたが
正直言うと大学院に入学してから得られた知識すべてが
臨床で活かされていると思います。

それを目的に大学院行ったしな。
そうなんです。
以前、大学院にどうして行きたいか書いたブログの中で
学び直しをしたいと言う考えがあると述べました。
ということで、現在その希望が叶っているということです^^^
もしこれから大学院生になろうと思うのであれば
私は背中を押したいとおもいますよ。
この内容が参考になれば幸いです。


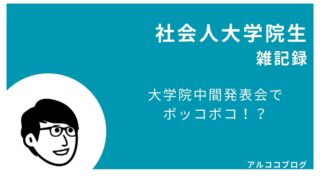
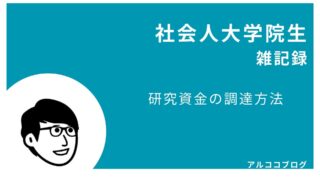

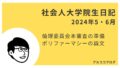
コメント